concept
生命の起源と初期進化を
追体験する
分子生命進化学研究室水内 良 准教授
担当科目:生命の起源、生命科学B
concept
生命の起源と初期進化を
追体験する
分子生命進化学研究室水内 良 准教授
担当科目:生命の起源、生命科学B
皆さんは生命がどのように誕生したと思いますか?一般的には、約40億年前の原始地球において、私たちの祖先となる細胞が非生命である分子から生まれたと考えられています。しかし、その痕跡はどこにも残っておらず、「生命の起源」は人類に課せられた大きな未解決問題です。当研究室ではこの謎に対し、分子から生命が誕生する過程を実験的に再現することで理解を目指しています。研究は生化学実験を基本とし、情報科学・コンピュータを用いたアプローチと組み合わせて行っています。
本研究室は2023年の新設になります。生命とは何かを知り、私たちの生まれを探究する研究は、社会の知的好奇心を大いに刺激し、人類の英知を広げます。これは大学でしかできない、純粋な科学的興味に基づく研究です。一方で、この分野はまだまだ未開拓の大きなフロンティアなので、研究の過程で新技術も多数生まれています。私自身はこのロマン溢れる研究を始めてはや10年ですが、日々謎に立ち向かう興奮を味わい続けています。特に知的好奇心と情熱に溢れる皆様を歓迎します。
 図1:水内研究室の研究概要。ここに示されていない研究も複数行っております。また皆さんにテーマを立案していただくことも歓迎します。
水内研究室では、「生命がどのように誕生したのか?」という疑問に答えるため、非生命である単純な分子から生命が進化する過程を実験的に再現しようとしています(分子生命進化学)。例えば自己複製する分子を実験的に進化させることで、どのように複雑化して生命に至るかを直接的に検証しています。また様々な分子を組み合わせて有り得た原始細胞を構築し、その特徴を理解することも目指しています。この過程で、ゲノム工学や進化工学、人工細胞に関する様々なバイオ技術の開発も行っています。研究は生化学実験を基本とし、情報科学・コンピュータを用いたアプローチと組み合わせて行います。生化学実験では主に分子生物学、進化生物学、生物物理学、合成生物学の手法を用いています。
図1:水内研究室の研究概要。ここに示されていない研究も複数行っております。また皆さんにテーマを立案していただくことも歓迎します。
水内研究室では、「生命がどのように誕生したのか?」という疑問に答えるため、非生命である単純な分子から生命が進化する過程を実験的に再現しようとしています(分子生命進化学)。例えば自己複製する分子を実験的に進化させることで、どのように複雑化して生命に至るかを直接的に検証しています。また様々な分子を組み合わせて有り得た原始細胞を構築し、その特徴を理解することも目指しています。この過程で、ゲノム工学や進化工学、人工細胞に関する様々なバイオ技術の開発も行っています。研究は生化学実験を基本とし、情報科学・コンピュータを用いたアプローチと組み合わせて行います。生化学実験では主に分子生物学、進化生物学、生物物理学、合成生物学の手法を用いています。
 図2:RNA
図2:RNA
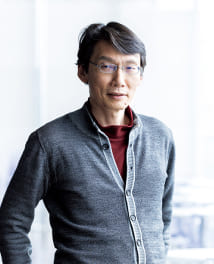 図2:人工細胞
図2:人工細胞
 図2:進化の系統樹
情報科学・コンピュータでは、バイオインフォマティクスと数理生物学を活用したビッグデータ解析 (進化解析など)やシミュレーションを行っています。また、他大学との共同研究も積極的に行っています。
図2:進化の系統樹
情報科学・コンピュータでは、バイオインフォマティクスと数理生物学を活用したビッグデータ解析 (進化解析など)やシミュレーションを行っています。また、他大学との共同研究も積極的に行っています。
具体的な研究例を紹介します(図1)。
【a】原始的な自己複製分子(RNA)を探究する。
近年、コロナウイルス関連でRNA(核酸分子)という言葉をよく耳にするようになりました(図2左)。実はこのRNAこそが、原始地球で生まれた最初の自己複製体だったと考えられています。私たちは、(i) あり得た自己複製RNAを設計し、(ii)無秩序な有機物のスープから出現させ、(iii) さらに進化させることで、生命の起源における第一歩を直接的に理解しようとしています。バイオインフォマティスの技術を用いて1000万種類以上の大規模なRNA配列のデータを扱うこともあります。
【b】人工細胞 (生命のモデル)を試験管内で作る。
様々な特徴をもつ細胞をその部品から組み上げ、生命の仕組みを理解し、また原始生命モデルとして利用します(図2中央)。例えば (i) 脂質膜にゲノムやタンパク質を封入してゲノム複製する人工細胞を構築し、研究 (c) で進化させます。近年は (ii) 細胞膜を持たないより原始的な細胞(想像できるでしょうか?)を作って特徴を調べたり、(iii) (生命の起源とは別に)人工的に多細胞を作り、多細胞現象の理解も目指しています。また人工細胞は「生きた細胞」では難しい物質生産や化学反応の場として利用でき、新規のバイオ技術開発にも繋がります。
【c】原始生命モデルを進化させる。
この研究では、進化する人工細胞を用いて、分子をどんどん進化させていきます(図2右)。人工細胞には自己複製に必要な情報(遺伝子)をもつRNAゲノムが入っており、エサを与えれば勝手に複製して進化します。特に原始的な生命システムがどのように複雑化していくかを検証しており、現在は (i) 進化によって新しい機能が生まれる条件、(ii) 進化が止まる場合の原因、(iii) 細胞構造の違いが生み出す進化の違いなどを明らかにしたいと考えています。シミュレーションも組み合わせて研究を進めることがあります。
以上のように、私たちの研究は多様な分野を融合した学際的な領域です。国内ではもちろん、世界的に見ても非常に新しく、その独自性が高く評価されています。当研究室で研究すれば、多様な知識と技術を身に着けるとともに、新しい科学を自ら切り拓く能力を育み、どのような将来を歩もうと活躍できる人になってもらえると信じています。そのために私も皆さんを全力でサポートすることを約束します。
【研究のキーワード(一例)】生命の起源、実験進化、進化工学、分子、RNA、構造、自己複製、ゲノム、タンパク質、人工細胞、生命システム、無細胞翻訳系、再構成、複雑性、ネットワーク、協力、寄生、生態系、液―液相分離、分子通信、多細胞
【関連する学問分野】分子細胞生物学、生化学、前生物化学、進化生物学、宇宙生物学、生物物理学、合成生物学、バイオインフォマティクス